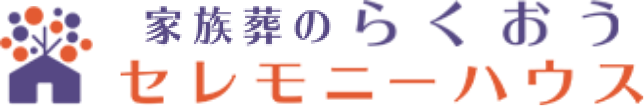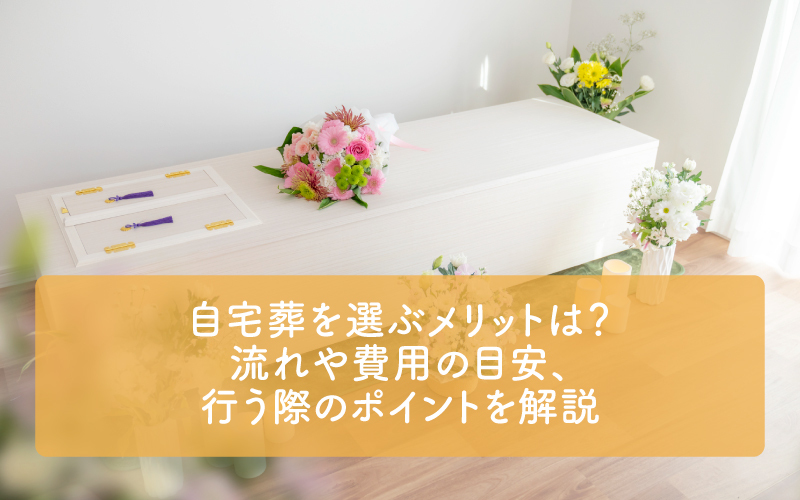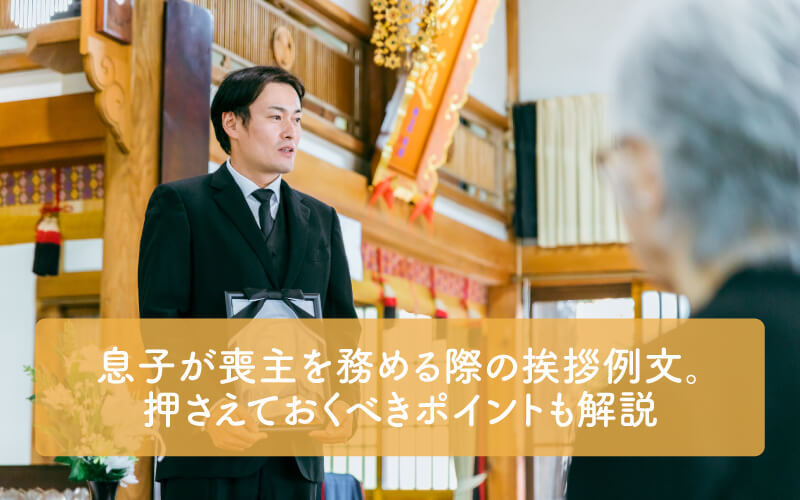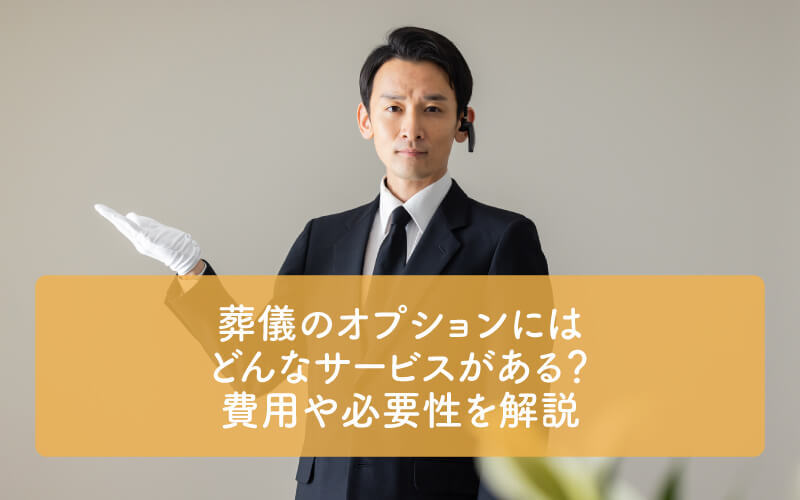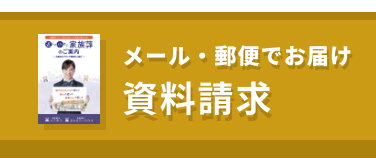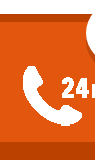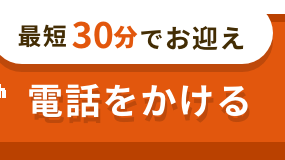自宅葬とは、その名のとおり、故人の自宅で行う葬儀を指します。地域にもよりますが、現在では、葬儀は斎場やセレモニーホールで行うケースが主流です。しかし日本では、元々自宅で葬儀を執り行うことが一般的でした。近年、葬儀の形式が多様化する中で、昔ながらの葬儀の形である自宅葬を検討する方もいるのではないでしょうか。
一般住宅で行う自宅葬には、葬儀専門の施設である斎場とは異なるポイントや注意点があります。ここでは、自宅葬を選ぶメリットやデメリット、自宅葬にかかる費用の目安のほか、自宅葬を検討する上で確認しておきたい注意点についても解説します。
自宅葬とは故人の自宅で行う葬儀の形式
自宅葬とは、故人が生前住んでいた家で執り行う葬儀の形式です。
自宅葬は、故人が長年親しんだ自宅を会場とするため、斎場などに比べてプライベートな雰囲気で葬儀を執り行うことができます。また、会場や時間の制約が少なく、より自由な形式で葬儀を行えるという特徴があります。
自宅葬を選ぶ人は減少傾向
自宅葬は、日本で古くから行われてきた葬儀の形式です。しかし現在では、自宅葬は減少傾向にあり、斎場などで行うケースが主流といわれています。自宅葬が減っている背景には、主に以下のような理由が考えられます。
-
<自宅葬を選ぶ人が減っている理由>
・自宅よりも病院で亡くなるケースが増えている
・集合住宅で暮らす人が増えている
・斎場やセレモニーホールなどで行うほうがご遺族への負担が少ない
上記に加えて、自宅葬が減少している要因としては、近年の生活環境の変化も挙げられるでしょう。自宅で葬儀を行うには、それなりに広いスペースや、近所の人の手伝いなどが必要です。ただ、特に都市部においては、核家族化が進んでマンションなど集合住宅で暮らす人が増え、近所付き合いも希薄化していると考えられます。このような環境においては、斎場や葬儀会場で葬儀を行うほうがご遺族の負担が少なく済むため、自宅葬を選ぶ人は昔に比べて少なくなってきました。
一方で近年、葬儀の形式は多様化しています。「近しい人たちだけで故人を見送りたい」「よりプライベートな空間で故人を偲びたい」など、故人の生前の意向やご遺族の希望によって、自宅葬が選択されるケースもあります。
自宅葬を選ぶメリット
自宅葬には、斎場などで行う葬儀とは異なるさまざまなメリットがあります。自宅葬を選ぶ場合の主なメリットを、以下にご紹介します。
故人が住み慣れた環境でお別れができる
自宅葬のメリットのひとつは、故人が住み慣れた環境でお別れができることです。「愛着のある我が家で最期を迎えたい」と希望する方は少なくありません。自宅葬であれば、病院や施設で亡くなったとしても、「自宅に帰りたい」という故人の最期の希望を叶えることができます。
また、葬儀の会場が自宅であれば、故人の思い出の品などを準備するのもスムーズです。ご遺族や弔問客もリラックスでき、和やかな雰囲気で故人の思い出を共有しやすいでしょう。
時間や形式の制限が少ない
葬儀の時間や形式に制限が少ないことも、自宅葬のメリットといえます。斎場などで行う場合は、会場の都合で葬儀の時間が決められており、その流れに沿って進行する必要があります。ゆっくり故人を見送りたいと思っても、時間の制約上難しいことがあるかもしれません。
反対に、自宅葬であれば、自宅が会場となるため、時間を気にせず通夜や葬儀・告別式を執り行うことができます。また、自宅葬なら自由に式が進行しやすいので、細かい作法やルールにとらわれる必要もありません。落ち着いて故人とのお別れのひとときを過ごせます。
費用負担を抑えられる可能性がある
自宅葬を選ぶと、斎場やセレモニーホールといった施設料がかからないため、葬儀にかかる費用の負担を抑えられる可能性があります。特に葬儀社を介さずご遺族や親族だけで自宅葬を行う場合は、通夜や葬儀・告別式にかかる費用を抑えられるでしょう。
ただし、現実的には、自宅葬の準備や儀式をすべて自分たちだけで行うのは難しく、葬儀社に依頼するケースが一般的です。自宅葬を葬儀社に依頼する場合はセット料金が設定されていることが多く、一概に費用が安くなるとは限りません。かかる費用は葬儀社によって異なるので、あらかじめ見積もりを取って検討する必要があります。
自宅葬を選ぶデメリット
上に挙げたようなメリットがある一方で、自宅葬にはデメリットもあります。自宅葬を選ぶ場合には、メリットとデメリットの両方を理解することが大切です。
近隣住民への配慮が必要になる
自宅葬は自宅が葬儀会場になるため、当日は棺を運び入れたり、喪服を着た弔問客が何人も訪れたりすることになります。また、話し声が近所迷惑になってしまうケースも考えられます。トラブルを防ぐためにも、あらかじめ自宅葬を行うことをご近所に伝え、理解を得ておきましょう。また、弔問客のための駐車場を確保しておくなど、周りに迷惑がかからないように配慮する必要があります。
ご遺族の負担が増える
葬儀用にしつらえられた斎場で行う葬儀とは違い、自宅葬では、準備や後片付けにかかる遺族の負担が増えてしまいます。どのような自宅葬を行うかによっても異なりますが、祭壇の設営や供花の飾りつけなど、必要な準備は斎場などで行う場合とあまり変わらないケースもあります。場合によっては、会食をする部屋や僧侶の控室などの準備も必要です。
自宅葬でも葬儀社のサポートを受けることは可能ですが、斎場やセレモニーホールなどで行う葬儀に比べると、ご遺族や親族の負担が増えてしまうのはデメリットといえます。
集合住宅では自宅葬が禁止されている場合がある
現代では、マンションやアパートなど集合住宅に暮らす人も増えています。自宅が集合住宅の場合、規約によって自宅葬が禁止されていることがあるため注意しましょう。たとえ禁止されていなくても、自宅に十分なスペースが確保できないなど、物理的に自宅葬を行うのが難しいケースもあります。集合住宅で2階以上に自宅がある場合は、エレベーターや階段で棺を運べるかという問題もあります。
自宅葬の流れ
ここからは、一般的な自宅葬の流れについて解説します。
自宅葬は喪主やご遺族だけですべて執り行うことも可能ですが、ご遺体の取り扱いなど慣れないことも多く、準備や後片付けなど負担も大きくなりがちです。葬儀社に依頼すれば専門知識を持ったスタッフのサポートを受けられるため、準備や進行などを任せやすいでしょう。
葬儀社に依頼する場合の一般的な自宅葬の流れは、以下のとおりです。
-
<自宅葬の主な流れ>
1. 故人のご臨終
2. 葬儀社へ連絡
3. 通夜
4. 葬儀・告別式
5. 火葬・収骨
1. 故人のご臨終
故人が自宅で亡くなった場合は、かかりつけの病院に連絡を入れてください。かかりつけ医がいない場合は救急車を呼び、指示を仰ぎましょう。場合によっては警察への連絡が必要です。医師の死亡確認後、死亡診断書を受け取ります。死亡診断書は死亡届と一体になっていることが一般的で、故人の死亡の事実を知った日から7日以内に役所へ提出する必要があります。
2. 葬儀社へ連絡
故人のご臨終後、できるだけ早く葬儀社へ連絡を入れましょう。このとき、自宅葬を行いたい旨を葬儀社へ伝えてください。もし病院や施設などで亡くなった場合は、依頼した葬儀社が、寝台車でご遺体を自宅まで搬送するケースが一般的です。そのほかにも、葬儀社は、ご遺体の安置や、祭壇の設置、式の進行の手配などを行ってくれます。なお、ご自宅の状況によっては、家具を動かすなどの作業が必要になります。
3. 通夜
ご遺体を棺に納める納棺の儀や、会場の設営を経て、通夜を執り行います。通夜は、近しい方々が集まり、故人との思い出を共有する時間になります。通夜の後は、通夜振る舞いと呼ばれる会食の席を設けるのが一般的です。
なお、自宅葬で通夜や葬儀・告別式に僧侶を招くかどうかは、故人や家族の考え方などによって異なります。もし僧侶による読経を希望する場合は、事前に菩提寺に相談するか、葬儀社に手配を依頼しましょう。
4. 葬儀・告別式
通夜の翌日または数日後に、自宅にて葬儀・告別式を執り行います。葬儀社に依頼している場合、基本的には葬儀社のスタッフが進行をサポートしてくれます。ただ、自宅葬でどこまで対応してもらえるかは葬儀社によって異なるため、事前に相談するとよいでしょう。
5. 火葬・収骨
葬儀・告別式の後は霊柩車にて自宅から火葬場へ移動し、ご遺体の火葬を行います。火葬後には、灰になっていないお骨を骨壺に収めます。
自宅葬にかかる費用の目安
自宅葬にかかる費用の目安は、すべてをご遺族・親族で行う場合と、葬儀社に依頼する場合とで大きく異なります。それぞれのケースごとに、費用の目安を見ていきましょう。
ご遺族・親族で取り仕切る場合:10万円前後
葬儀社に依頼せず、すべてをご遺族・親族で取り仕切るのであれば、費用の目安は10万円前後となります。ただしこれは、祭壇の設置や僧侶の読経などを行わず、無宗教の自由形式で行う自宅葬の場合です。棺や骨壷はインターネットで購入したり、単品販売に対応している葬儀社から購入したりする方法があります。
なお、宗教者に読経などの宗教儀式を行っていただく場合は、祭壇の準備やお布施など、必要となる物品や費用が増える点に注意が必要です。
葬儀社に依頼する場合:40万円以上
自宅葬を葬儀社に依頼して執り行う場合は、40万円以上がひとつの目安です。
一般的に、葬儀社のセットプランには、祭壇や棺、骨壺、ドライアイスといった自宅葬に最低限必要な物品が含まれています。ただし、セットプランに何が含まれているかは葬儀社によって異なるため、事前に見積もりを取り、内容や金額の詳細を確認しておきましょう。
また、葬儀社に依頼した場合でも、宗教者へのお布施や参列者への返礼品のほか、通夜振る舞いなどの会食にかかる飲食接待費は別途必要です。
あわせて読みたい
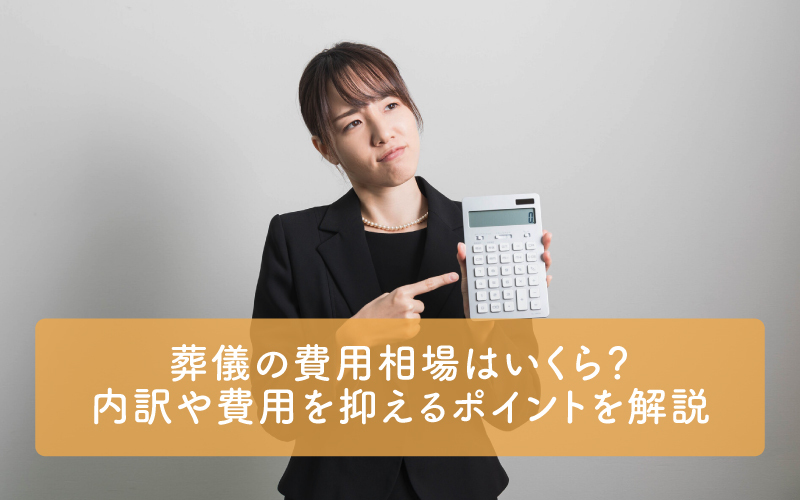
葬儀の費用相場はいくら?内訳や費用を抑えるポイントを解説
家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクターの東條です。葬儀にはお金がかかるものというイメージがあると思いますが、実際にかかる金額は葬儀の種類や内容、お住まいの地域などによっ...
あわせて読みたい

【自宅葬とは?】その特長や費用、流れをご紹介します
家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクター北村です。近年、特に都市部では葬儀を斎場やセレモニーホールを貸し切って行うケースが大半ですが、「大切な方を、住み慣れた...
自宅葬を行う場合の注意点
自宅葬を行う際には、前述したメリット・デメリットのほかにも、押さえておきたい注意点があります。滞りなく葬儀を執り行えるように、以下のポイントに十分注意しましょう。
自宅葬のためのスペースを確保する
自宅葬の形式によっても異なりますが、自宅葬を行うにはご遺体を安置したり、祭壇を設置したりするスペースに加え、ご遺族や参列者が座るためのスペースも確保しなければなりません。参列者が少ない小規模な形であっても、6畳以上のスペースは必要になると考えられます。参列者の人数によってはさらに広い部屋が必要となり、宗教者を呼ぶ場合は控室の準備も必要です。自宅に葬儀を行えるだけのスペースがあるか、事前によく検討しておきましょう。

また、玄関や廊下に棺を運べるスペースがあるかを確認することも大切です。特に集合住宅の場合は、エレベーターや階段、共用廊下にもそれなりの広さが必要になります。なお集合住宅によっては、住民用とは別に大型のエレベーターがあったり、大きな物を運べるようにエレベーターの背面が開くつくりになっていたりすることもあります。
賃貸住宅の場合は家主の許可を得ておく
賃貸住宅で自宅葬を行いたいと考えている場合は、必ず事前に家主の許可を得ましょう。集合住宅の規約で禁止されていなくても、家主によっては、自宅で葬儀が行われることを嫌がるケースもあります。もし家主が自宅葬を許可しなければ、葬儀の形式を変更しなければなりません。葬儀直前で慌てる事態にならないように、早めに家主に相談して許可を得ておくことが大切です。
近隣住民への配慮を大切にする
自宅葬を行う際には、近隣住民へ十分に配慮する必要があります。自宅葬では、棺や弔問客のほか、ご遺体を運ぶための霊柩車の出入りもあります。周囲に与える影響を考慮し、事前にきちんと説明をしておかなければなりません。近隣住民から了承を得た上で自宅葬を行うことは、故人を穏やかに送り出すためにも大切です。また、自宅葬を無事に終えたら、近隣の方に報告をするとともに謝意を伝えましょう。
自宅葬のメリット・デメリットを踏まえて検討しよう
故人が慣れ親しんだ自宅で行う自宅葬は、形式にとらわれずプライベートな雰囲気で葬儀を行うことができ、斎場などで行う葬儀に比べて費用を抑えられる可能性もあります。その一方で、自宅葬は、準備や後片付けにかかるご遺族の負担が増えたり、近隣住民への配慮が必要だったりするデメリットもあります。そもそも、自宅で葬儀を行えるだけのスペースを確保できるかという問題もあるでしょう。葬儀の形式を決める際には、家族の希望や自宅の状況などを踏まえて検討することが大切です。
また、自宅葬は喪主やご遺族だけで取り仕切ることもできますが、難度が高いので、葬儀社に依頼してサポートを受けるケースが一般的です。ただ、自宅葬に対応できるか、どこまでのサポートが可能かなどは、葬儀社によって異なります。そのため、葬儀形式や自宅葬に関する疑問がある場合は、事前に葬儀社に相談するのがおすすめです。
家族葬のらくおう・セレモニーハウスなら、葬儀にまつわるお電話での事前相談を24時間365日、無料で受け付けています。メールや対面でもご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
よくある質問
Q1.自宅葬とは何ですか?
自宅葬とは、故人が生前住んでいた自宅で執り行う葬儀の形式です。自宅葬には、斎場などで行う葬儀と比べて、プライベートな雰囲気で葬儀を行えるという特徴があります。また、時間の制約が少なく、より自由な形式で葬儀を執り行うことができます。
Q2.自宅葬のメリットとデメリットは何ですか?
自宅葬のメリットは、故人が住み慣れた環境で、時間や形式に縛られずにお別れができることや、斎場などで行うよりも費用負担を抑えられる可能性があることです。デメリットとしては、自宅葬を行う際には近隣住民への配慮が求められるほか、準備や後片付けにかかるご遺族の負担が増えることなどが挙げられます。また、集合住宅によっては自宅葬が規約で禁止されている場合もあるため、事前確認が必要です。
Q3.自宅葬にかかる費用はどれくらい?
自宅葬にかかる費用は、祭壇などを設置せずにすべてをご遺族・親族で執り行う場合は10万円前後、葬儀社に依頼して祭壇の設置や宗教儀式を行う場合は40万円以上が目安です。そのほか、必要に応じて、宗教者へのお布施や参列者への返礼品、飲食接待費などが別途かかります。
京都・大阪・滋賀・兵庫・石川県のご葬儀は家族葬のらくおう・セレモニーハウスへ
家族葬のらくおう・セレモニーハウスでは、家族葬、一日葬、火葬式・直葬、福祉葬などのご葬儀を安心の低価格で執り行っております。家族葬のらくおう・セレモニーハウスでのご葬儀は、下記よりお気軽にご依頼・ご相談ください。専門スタッフが24時間365日、いつでも対応しております。
アフターサポートの詳細はこちら