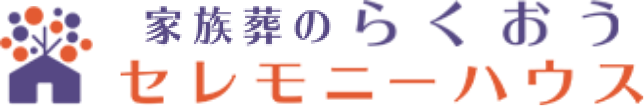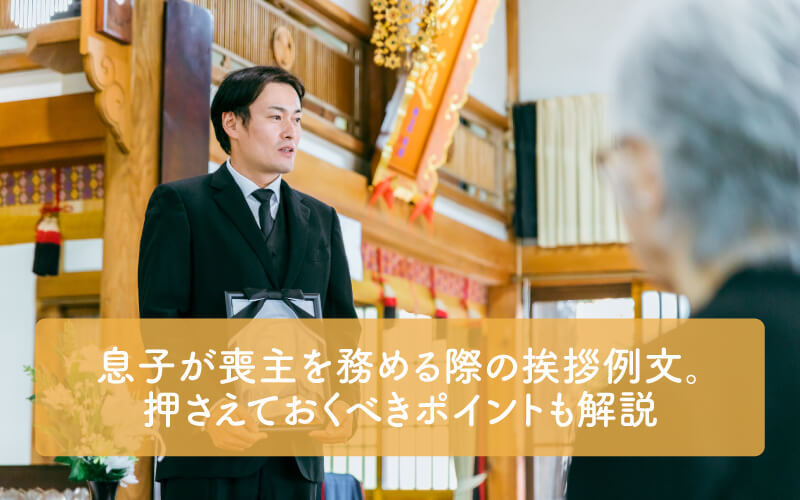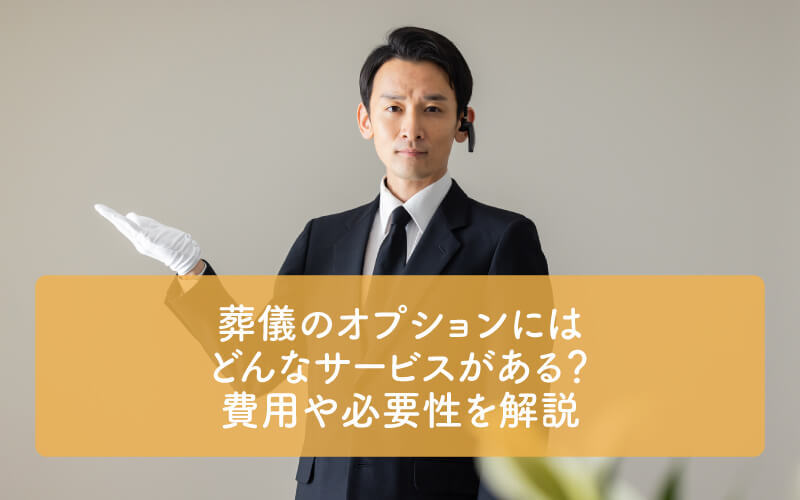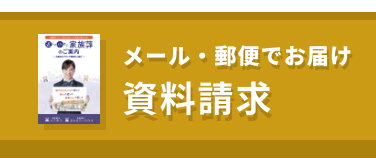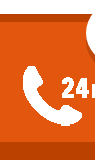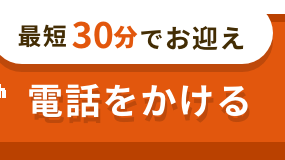家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクターの朝田です。
日本では、葬儀を終えたご遺体を火葬によって弔うのが一般的です。しかし初めて火葬を経験される方にとっては、「火葬にはどのくらいの時間がかかるのか」、「火葬の待ち時間は何をして過ごすのか」など、わからないことも多いのではないでしょうか。
今回は、火葬の流れや火葬にかかる時間、待ち時間の過ごし方など、みなさんが火葬に対して疑問に思うことを、一つずつ解消していきたいと思います。
火葬の流れ
①葬儀後、火葬場へ出棺
葬儀を終えた故人様のご遺体は、葬儀場から火葬場へと出棺されます。
②遺族・親族ら近しい方々は、火葬場へ移動する
火葬に立ち会えるのは、故人様と関係の深い方々のみです。
一般的に、喪主は故人様の棺をのせた霊柩車の助手席に同乗して火葬場へ向かい、それ以外の関係者はハイヤーやマイクロバスなどを貸し切って火葬場に向かうことが多いです。(葬儀場から火葬場までの距離や人数によって移動手段は変わります。)
-
【移動手段の例】
自家用車で各自向かう
ハイヤーを予約する・・4〜10名前後
マイクロバスを貸し切る・・20名前後
大型タクシーを貸し切る・・10名前後
また、火葬場へは僧侶も同行するのが一般的ですが、その場合は事前に移動手段を確認し、必要であれば僧侶も人数に加えて移動車を手配するようにしましょう。
③火葬許可証を提出する
火葬場では、係員の指示に従って最初に火葬許可証を提出します。火葬許可証とは、死亡届を提出した際に役所で発行される書類のことです。
④納めの式・火葬
火葬場の前で、最後のお別れの儀式が執り行われます。僧侶による読経の後、関係の深い方から順に焼香を行うのが一般的です。その後火葬が執り行われます。この時、位牌と遺影写真は火葬炉の前に飾られます。
⑤お骨上げ・収骨
火葬が終わったら収骨室に集まり、故人様のお骨を二人一組で拾いあげ、骨壷に収める収骨が行われます。
⑥骨箱(骨壷・埋葬許可証)を受け取る
すべてのお骨を収め終えたら、骨壷の入った骨箱を受け取ります。骨箱の中には骨壷と埋葬許可証(火葬許可証に押印されたもの)が入っています。この埋葬許可証は、納骨の際に必要となるため、ご自宅で大切に保管しましょう。
火葬にかかる時間は1時間前後
火葬にかかる時間は、故人様の体型や棺の中に収めた副葬品によって前後します。目安としては大人の方で1時間〜1時間半、お子さんで40分程度となります。体格が大きければ大きいほど、また副葬品の量が多ければ多いほど、火葬には時間がかかることを覚えておきましょう。
また火葬後の収骨などを含めれば、火葬場での滞在時間は正味2時間程度となることが一般的です。
【補足】火葬炉の種類による火葬時間の違い
厳密には、火葬炉の種類によっても火葬時間は前後します。火葬炉には「台車式」と「ロストル式」の2種類があり、日本の火葬炉は「台車式」のものが多いです。「台車式」は、ご遺骨を人型の状態で残しやすく、衛生管理がしやすいという特徴がありますが、「ロストル式」に比べると火葬時間が若干長くなります。とはいえ、「台車式」で60〜70分、「ロストル式」で60分前後と言われているため、そこまで大きな差はありません。
火葬時間を左右する副葬品の選び方
前述の通り、火葬時間は故人様の体型と棺に収める副葬品によって決まります。そもそも棺には副葬品として入れて良いものといけないものがあります。スプレー缶やライターなど爆発の恐れがあるものや、革製品やプラスチックのように燃やすことで有害物質を発生させるものなど禁止される品は入れないように注意しましょう。
また前述の通り、副葬品が多いほど火葬時間は長くなってしまうため、故人様がどうしても入れて欲しいと言っていたものを優先し、最小限にすることも大切です。どうしても入れたいものがある場合は、写真に撮って入れるなどの工夫をするという方法もあります。
火葬の待ち時間の過ごし方
次は、火葬の待ち時間にすべきことについてお伝えします。火葬の待ち時間には、控室やロビーで待機するか、会食をして過ごすことが一般的です。
控室やロビーで過ごす
基本的には、火葬場の控室やロビーで待機します。お手洗いを済ませたり、タバコを吸う方はこの間に吸われる方も多いです。控室には、お茶やお菓子などが用意されていることもあるので、そちらをいただきながら過ごすこともできます。
また火葬場には売店や自動販売機があるところも多いため、軽食や飲み物を買って小腹を満たすこともできるでしょう。
精進料理をいただく
本来精進料理とは、四十九日の忌明けにとる食事のことをいいますが、現代においては、火葬中、もしくは火葬後の会食の際にいただく料理のことを言うことが多くなっています。
火葬後に、レストランなどを予約して会食の席を設ける場合もありますが、火葬の待ち時間に仕出し料理等を利用して、みなさんで会食をとる場合もあります。いずれの場合もレストランや仕出し屋さんに、事前に予約をしておく必要があります。火葬中に控室で仕出し料理をいただく場合は、葬儀社に手配を任せることも可能ですが、火葬後にレストランを利用する場合は、ご自身での予約が必要となります。レストランを予約する際には、必ず先方に精進落としで利用する旨を伝えましょう。きちんと伝えておかないと、場にそぐわないエビや鯛などのおめでたい料理が出てきてしまうことがあります。
火葬をするタイミングはいつ?
ここまで、火葬の流れや火葬にかかる時間、火葬場での過ごし方についてお伝えしてきましたが、そもそも、火葬はどのタイミングで行われるものなのか疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれません。
日本においては「火葬は死後24時間経過後に行う」ことが法律で定められているため、ご逝去から24時間は、ご自宅や安置施設等でご遺体を安置したのちに、火葬を執り行う流れになります。通常は、お亡くなりになった翌日にお通夜、翌々日に葬儀・告別式を行い、葬儀・告別式と同日に火葬となることが多いです。
また、最近は直接火葬場でお別れをする「火葬式・直葬」を選ばれるご家族様も増えていますが、その場合もご逝去後24時間はどこかでご遺体を安置する必要があるため、いずれにしてもご逝去の翌々日が最短の火葬日程となることを覚えておきましょう。
家族葬のらくおう・セレモニーハウスの直葬・火葬式プラン
火葬を行う時間帯に決まりはある?
火葬を行う時間帯に、特に決まりはありませんが、ほとんどの場合、火葬は午前中に行われています。火葬場の閉館時間は17時頃のことが多いですが、もし火葬開始時間が15時をすぎてしまった場合は、その日のうちに収骨までを行うことができなくなってしまうため注意が必要です。そのため火葬場は11:00〜12:00の間に最も混雑すると言われています。
まとめ
いかがだったでしょうか。火葬時間は故人様の体型や副葬品によって前後はしますが、大人であれば、約1時間程度が目安となります。その間、関係者は控室などで待機をするか、場合によっては精進落としの席が設けられることもあります。火葬後は収骨を行い、最終的には故人様のお骨の入った骨壷と埋葬許可証を受け取って終了となります。
これから火葬を執り行う方は、ぜひ参考にしてください。
京都・大阪・滋賀・兵庫・石川県のご葬儀は家族葬のらくおう・セレモニーハウスへ
家族葬のらくおう・セレモニーハウスでは、家族葬、一日葬、火葬式・直葬、福祉葬などのご葬儀を安心の低価格で執り行っています。また火葬に関する手続きや火葬場とのやりとりもお客様に代わって私たちスタッフが行いますので、安心してお任せください。
家族葬のらくおう・セレモニーハウスへのご葬儀のご依頼・ご相談は、24時間365日下記より承っています。