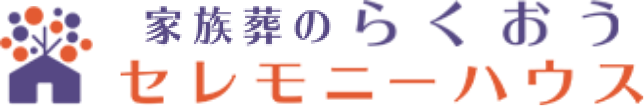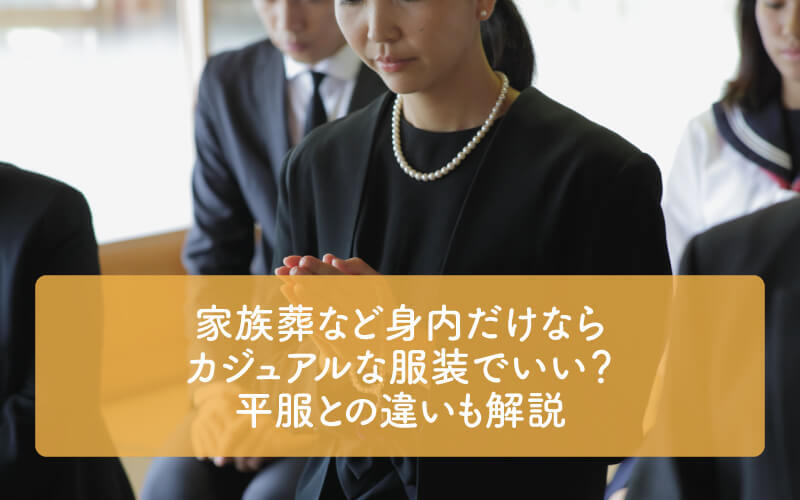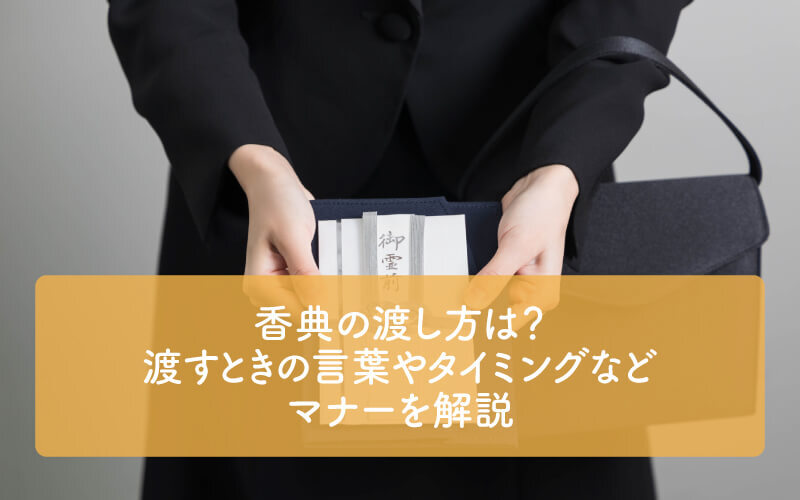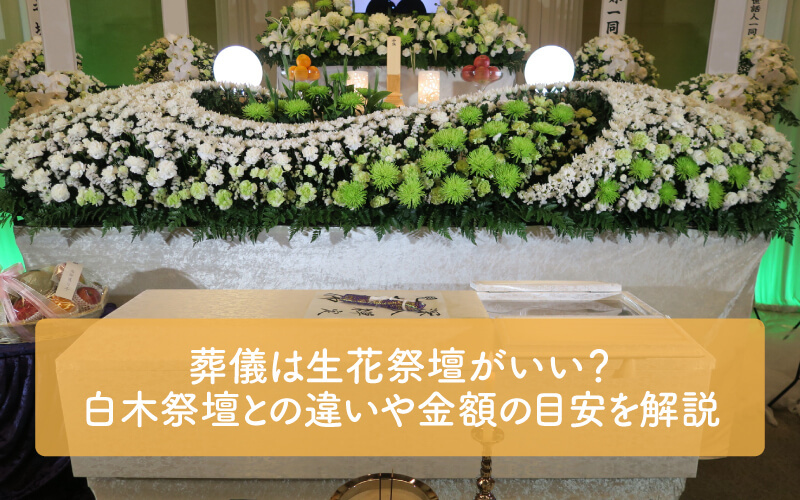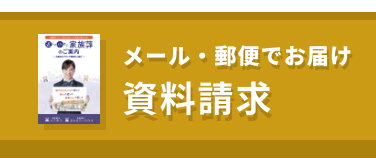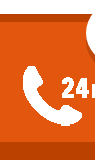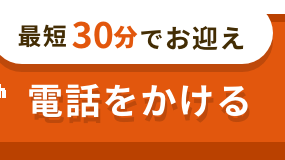家族葬のらくおう・セレモニーハウスの相談員の遠藤です。
葬儀は、遠方からの親族などが一堂に会する機会でもあるため、記録写真や集合写真を撮る機会もあると思います。また、故人との思い出として、葬儀の様子を写真に残しておきたいという人も多いでしょう。しかし、葬儀の場で撮影はマナー違反に当たらないのでしょうか 。実際に、そういった疑問は、多くの方がお持ちなのではないかと思います。
今回は、葬儀での写真撮影のマナーについて、注意すべき点やポイントなども交えて解説したいと思います。これから葬儀を行うご遺族はもちろん、葬儀に参列するご予定のある方も、ぜひ参考にしてください。
葬儀での撮影は可能かどうかの事前確認が必要
葬儀の場では、撮影可能なこともありますが、勝手に撮影をすることはマナー違反となってしまうため、必ず、ご遺族や斎場など周囲に確認をした上で撮影を行いましょう。葬儀の場では、普段集まることがない親戚や友人・知人らが一堂に会する機会でもあるため、集合写真を撮るという流れになることもあるでしょう。また、ご遺族が故人との思い出として、祭壇の写真などを残しておくために撮影するということもあるかと思います。
しかし、公営の斎場やお寺などの宗教施設、火葬場などでは、プライバシー保護の観点や、宗教上の理由から、撮影禁止のところも少なくありません。葬儀の場で撮影が可能かどうかは、地域や施設、あるいは宗教などの違いによっても異なりますので、必ず事前に許可を得た上で撮影し、不謹慎と思われる行為をしないことが大切です。
葬儀での写真撮影の際に注意したいポイント
葬儀での写真撮影は、周囲に迷惑をかけないように行うことが大切です。撮影の際には、以下のポイントに注意しましょう。
-
葬儀での写真撮影の際に注意したいポイント
・進行の邪魔をしない
・シャッター音やフラッシュに配慮する
・人物を勝手に撮らない
・勝手に画像を共有しない
進行の邪魔をしない
読経中の僧侶や、焼香中の参列者など、宗教儀式を行っている際の撮影は不可となることも多いです。無理に撮影すると進行の妨げになってしまうため、許可を得ていない撮影は控えるようにしましょう。また、祭壇に背を向けての撮影は、故人に背を向けることと同じと捉えられてしまい、不謹慎と感じる人も少なくありません。葬儀の場では、ご遺族や参列者に不快感を与えてしまわないよう、細心の注意を払うよう心がけましょう。
ただし、一部の地域では、祭壇をバックに遺族らが記念撮影をすることが慣例となっている地域もあるようです。その場合は、地域ルールに従って問題ないでしょう。
また、どんなに配慮をしていたとしても、葬儀での写真撮影そのものが、誰かを不快に感じさせてしまう可能性は否めません。そのため、もしご遺族から写真撮影を頼まれているという場合には、「記録係」と書かれた腕章をつけて撮影するなど、許可を得て撮影していることがわかるようにしておくのも一つの方法です。
シャッター音やフラッシュに配慮する
写真撮影の際には、シャッター音やフラッシュに気をつけましょう。たとえばスマートフォンでの撮影なら、無音のカメラアプリをダウンロードし、フラッシュはオフモードに設定しておくなど、事前準備をして臨むことが大切です。
人物を勝手に撮らない
葬儀の場における人物の撮影は、特に注意が必要です。ご遺族や参列者の中には、悲しんでいる顔を残されたくないと思う方も多いため、必ず許可を得てから撮影するようにしましょう。また、背景に人物が写り込んでしまわないよう気を配ることも大切です。
ご遺体の撮影についても、賛否が分かれるところかと思いますが、基本的には親族が写真に残しておくために撮影する場合は問題ないとされています。ただし、第三者が勝手に故人のお顔を撮影することは、遺族に対して失礼にあたるため、やめた方がよいでしょう。
勝手に画像を共有しない
撮影の許可を得ていたとしても、誰かに画像を共有する際や、SNSなどに投稿する際には、必ず遺族の許可を得る必要があります。葬儀写真に限らずですが、SNSに勝手に写真をアップされたなどのトラブルも多く、特に不特定多数の目に触れるSNSのような媒体に関しては、写真に対するリテラシーが問われています。とりわけ葬儀は、厳粛な宗教儀式の場でもあるため、ご遺族の感情に配慮し、無闇に他の人と写真を共有しないように注意しましょう。
撮影は葬儀社に依頼するという選択肢もある
葬儀の撮影は、葬儀社やプロのカメラマンに依頼するという方法もあります。そうすることで、遺族は葬儀に集中することができますし、プロのカメラマンに依頼するのであれば高品質な仕上がりが期待できます。また、周囲に配慮することもできるため、トラブルが起きにくいというメリットがあります。
ちなみに、プロのカメラマンに撮影を依頼する場合の費用は、5万円〜20万円程度が相場となっています。カメラマンによっては写真データだけでなく、DVDなどにまとめてくれるサービスを行っていることもあるため、依頼する際は、サービス内容を比較検討した上で決めるとよいでしょう。
葬儀写真の撮影に困ったら葬儀社などに相談を
葬儀での写真撮影は、事前にご遺族や斎場などの施設に確認をしてから行いましょう。施設によっては写真撮影が禁止されている場合もあります。また、故人とのお別れの時間を大切に過ごすためにも、撮影はプロに任せることも選択肢の一つです。葬儀の写真撮影についてわからないことがあれば、まずは葬儀社に相談してみましょう。
家族葬のらくおう・セレモニーハウスなら、葬儀にまつわるお電話での事前相談を24時間365日、無料で受け付けています。メールや対面でもご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
よくある質問
Q1.葬儀で写真撮影は不謹慎ですか?
葬儀での写真撮影は、マナーを守った上で行えば問題はありません。ただし、場合によっては撮影が禁止されていることもあるため、事前に遺族や斎場などの施設に許可を得ておく必要があります。また、遺影に背を向けての撮影は避けるなど、厳粛な葬儀の場であることを踏まえた節度ある行動が求められます。
Q2.葬儀中の撮影で注意すべきことは何ですか?
読経中の僧侶や焼香中の人物を撮影するなど、儀式の妨げになる撮影行為は避け、撮影時には、シャッター音やフラッシュをオフにしておくなど周囲に配慮した撮影を心がけましょう。また、人物を撮影する際には、必ず許可を得て行う必要があります。背景への人物の写り込みなどにも細心の注意を払いましょう。
Q3.葬儀の斎場で撮影は禁止されていますか?
公営の斎場やお寺などの宗教施設、火葬場などでは、撮影が禁止されていることも多いです。ただし、すべての斎場で禁止されているわけではないため、 葬儀の写真撮影を希望されている場合は、必ず遺族や会場となる施設に事前確認をするようにしましょう。事前に許可が得られていれば、撮影をすることは可能です。ただし、厳粛な葬儀の場での撮影となるため、マナーを守って撮影しましょう。
京都・大阪・滋賀・兵庫・石川県のご葬儀は家族葬のらくおう・セレモニーハウスへ
家族葬のらくおう・セレモニーハウスでは、家族葬、一日葬、火葬式・直葬、福祉葬などのご葬儀を安心の低価格で執り行っております。家族葬のらくおう・セレモニーハウスでのご葬儀は、下記よりお気軽にご依頼・ご相談ください。専門スタッフが24時間365日、いつでも対応しております。
アフターサポートの詳細はこちら